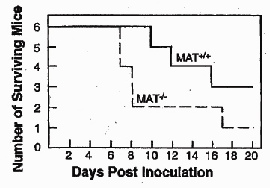
禁断の科学裁判
−−−ナウシカの腐海の森は防げるだろうか−−−
抗菌ペプチドの濫用がもたらす大きな危険性
−−人類の滅亡にもつながりかねない耐性菌の問題−−
金川貴博(元東京工業大学教授。専攻 )
11.4.2005
1.はじめに
抗菌剤を開発する場合に、まず第一番に考えないといけないのは、耐性菌の出現である。動植物が作り出す抗菌ペプチドを濫用して耐性菌が出現した場合、この耐性菌は、動植物への強力な感染力を持つことになり、深刻な問題を引き起こす。しかし、このことが、科学者間でも、あまり理解されていないようで、抗生物質の耐性菌と同列にしか考えられていないように思える。このために、耐性菌の持つ大きな危険性に何ら気づかずに行われている実験が、かなりありそうに思える。
2.抗菌ペプチドの役割と耐性菌の危険性
抗菌ペプチドの一種であるディフェンシン1)についての研究例を取り上げる。
まず、喘息患者とディフェンシンの関係である2)。喘息の治療に吸入ステロイド薬を使った場合、ステロイドで免疫が抑えられるので、ウィルスや細菌の感染による肺炎や気管支炎にかかりやすくなると考えられる。しかし、実際には感染が起こらない原因を調べた結果、ステロイド薬を使うと、気管支へ細菌が来たときに、その刺激で気管支から大量のディフェンシンが分泌されるということが明らかになった。つまり、ディフェンシンの抗菌抗ウィルス作用で、病原菌を撃退し、感染を防止していると考えられる。そこで、もしも感染予防にディフェンシンを安易に使用して、その結果として、ディフェンシン耐性の肺炎菌が出現したとしたら、これは恐ろしい結果をもたらすことになる。この耐性菌には、ディフェンシンによる防御が効かないので、強い感染力を持つことになり、多くの人が感染して肺炎を起こすことになる。ここが、抗生物質耐性菌の問題とは、根本的に異なる点である。
また、エイズ感染者で、長期にわたり発症しない人を調べてみると、α-ディフェンシンを作ることでエイズウィルスの活動を抑えているという結果が得られ、α-ディフェンシンがエイズウィルスの増殖を抑制することも実験で確認された3)。このため、エイズ治療に、ディフェンシンを使おうという発想がすでに出ているが、実際に使用した結果として、もしもエイズウィルスがα-ディフェンシン耐性を獲得した場合、患者は短期間でエイズを発症して死亡するものと考えられる。このように、ディフェンシン耐性は、病原菌の危険性を格段に高める結果をもたらすことになる。
また別の例として、サルモネラ菌(食中毒菌)をマウスに与えた実験が報告されている4)。マウスは、小腸の上皮細胞からディフェンシン前駆体を分泌し、病原菌が来ると、ディフェンシン前駆体の一部を切り取って、抗菌力のあるディフェンシンを作って、これで病原菌を攻撃して身を守るが、この実験では、抗菌力のあるディフェンシンを作れないマウスを使用して、普通のマウスの場合と比較している。まず、マウス6匹ずつに、289,000個のサルモネラ菌を与えたのが、下図の実験で、普通のマウス(図の実線)では10日目で1匹死んだのに対し、ディフェンシン欠損マウス(図の破線)は8日目までに4匹が死んでしまった。また、サルモネラ菌の数をいろいろに変えた実験では、マウスの半分が死ぬサルモネラ菌の数(LD50)は、普通のマウスでは114,000個なのに対し、ディフェンシン欠損マウスでは14,100個だった。つまり、ディフェンシン欠損マウスは、約十分の一の数のサルモネラ菌で死んでしまうという結果になった。もしも、与えたサルモネラ菌がディフェンシン耐性菌であった場合、普通のマウスでも、ディフェンシン欠損マウスと同様に、十分の一の数のサルモネラ菌で死んでしまうと考えられる。この実験も、ディフェンシン耐性菌が、普通の病原菌よりも大きな感染力を持つことを示している。
ディフェンシンなどの抗菌ペプチドについては、まだあまり研究が進んでいなくて、その詳細が十分には明らかになっていない段階であるが、このように、感染予防の第一線で大きな役割を果たしていることが次第に明らかになりつつある。このため、ディフェンシンを治療に使おうという考えも出てきているが、耐性菌の恐ろしさを考えると、十分に慎重に検討をしないと、人類を滅亡に導きかねない恐ろしい病原菌を生み出すことになる。これは単なる思い過ごしに過ぎないという人もいるが、動植物が作る抗菌ペプチドの研究が、まだあまり進んでいない現状においては、このような危険性を否定する材料がない。大きな危険性が予想される研究については、その危険性の有無についての確実な判断ができるようになるまで、実験を差し控えるべきであると考える。
3.耐性菌出現の可能性
ディフェンシンなどの抗菌ペプチドについては、耐性菌ができにくいという研究者たちもいる1,5)が、耐性菌の問題は、抗菌ペプチドの利用を考えている人たちにとって一番の障碍になるため、一部の文献を無視して、なるだけ耐性菌問題を軽く見ようとする意図が感じられて、危険に思う。
酵母(S. cerevisiae)を使った実験6)では、ブトウ糖20g/lを含む液体培地に、フジイロテンジクボタンが作るディフェンシンを5μM入れて、そこへ、酵母を1mlあたり100万から200万個になるように入れ、30℃で2日間培養した結果、ディフェンシン耐性の酵母が得られたと記載されている。このディフェンシン耐性酵母は、フジイロテンジクボタンが作るディフェンシンだけでなく、マロニエやチョウマメの作るディフェンシンにも耐性があり、通常の酵母なら1〜2μMで生育阻害を受けるのに、耐性酵母では40μM入れても、阻害されなかったと記載されている。
また、アカパンカビを使った実験7)では、ジャガイモ粉末を12g/l含む液体培地に、ダイコンのディフェンシンを4μM加え、アカパンカビの胞子を加えて、室温で5日間培養した結果、胞子340万個に1個の割合で、ディフェンシン耐性株が得られたとある。また、突然変異誘発剤のエチルメタンスルフォン酸で事前に胞子を処理すると、耐性株が40万個に1個の割合で得られたとある。
これらの文献は、培地にディフェンシンを入れて微生物を培養すると、容易に耐性微生物が出現することを示している。
しかしながら、これまで、自然界においてディフェンシン耐性菌が出現したという報告はない。耐性菌が出るか出ないかは、抗菌剤と病原菌との接触の頻度が大いに関係すると考えられる。その実例が抗生物質で、人為的に大量に使ったがために、耐性菌が出現し、これが蔓延する結果になった。そもそも、抗生物質を作る能力がある微生物といえども、常時抗生物質を出すのではないため、自然状態では、抗生物質と微生物とが接触する機会が少なく、耐性菌が出現する可能性が低い。同様に、ディフェンシンの場合も、動植物が必要に応じて生産するため、自然状態では、耐性菌が生じる可能性は低いと考えられる。
4.結語
動植物が生産する抗菌ペプチドの役割を理解すれば、これに対する耐性菌が出現した場合に、その脅威が大変に大きいことがわかる。したがって、危険な耐性菌を、万が一にも出現させてはならない。また、危険な耐性菌の出現につながるような行為は、絶対に行ってはならないのであるが、抗菌ペプチド耐性菌の危険性は、ほとんどまだ科学者間でも理解されておらず、危険な実験が野放しになっている。抗生物質耐性菌に比較して、危険の度合いが格段に高いのであるが、そのことが、なかなか理解してもらえないようである。
微生物は、短時間で増殖できるのであり、また、肉眼では見えないから、一度、危険な微生物が出現した場合に、その微生物を根絶やしにしたり、隔離したりするのは、非常に難しい。とにかく、危険な微生物を出現させないことが重要であり、その出現につながりそうな実験は行うべきではない。
文献
1)川田元滋、黒田秧、田中宥司:抗菌蛋白質ディフェンシンの多様な機能特性、化学と生物、43、229-234
(2005).
2) Homma, T., Kato, A., Hashimoto, N., Batchelor,
J., Yoshikawa, M., Imai, S., Wakiguchi, H.,
Saito, H., Matsumoto K.: Corticosteroid and
Cytokines Synergistically Enhance Toll-Like
Receptor 2 Expression in Respiratory Epithelial
Cells. Am. J. Respir. Cell Mol. Biol. 31,
463-469 (2004).
3) Zhang, L., Yu, W., He, T., Yu, J., Caffrey,
R. E., Dalmasso, E. A., Fu, S., Pham, T.,
Mei, J., Ho, J. J., Zhang, W., Lopez, P.,
Ho, D. D.: Contribution of human α-defensin
1, 2, and 3 to the anti-HIV-1 activity of
CD8 antiviral factor. Science, 298, 995-1000
(2002).
4)Wilson, C. L., Ouellette, A. J., Satchel,
D. P., Ayabe, T., Lopez-Boado, Y. S., Stratman,
J. L., Hultgren, S. J., Matrisian, L. M.,
Parks, W. C.: Regulation of intestinal α-defensin
activation by the metalloproteinase matrilysin
in innate host defense. Science, 285, 113-117
(1999).
5)Zasloff, M.: Antimicrobial peptides of multicellular
organisms. Nature, 415, 389-395 (2002).
6)Thevissen, K., Osborn, R. W., Acland, D.
P., Broekaert, W. F.: Specific binding sites
for an antifungal plant difensin from Dahlia
(Dahlia merckii) on fungal cells are required
for antifungal activity, Molecular Plant-Microbe
Interactions, 13, 54-61 (2000)
7)Ferket, K. K. A., Levery, S. B., Park, C.,
Cammue, B. P. A., Thevissen, K.: Isolation
and characterization of Neurospora crassa
mutants resistant to antifungal plant defensin,
Fungal Genetics and Biology, 40, 176-185
(2003).